
移動:HOME 画面
再入力
2025/11月******************************************************

|
■画像 a :20251127 コセイダングサの花の終わり 種子が開く前の姿 |
|---|

|
■画像 b :20251127 コセイダングサ種子の単体 この種子が大変厄介者です。草むらを歩くと2本のとげが衣服に刺さりなかなか取れません。 |
|---|

|
■画像 c :20251127 天道虫:太陽にむかっいて飛び立つ虫と言われ天への道を表している 通常はテントウムシ:冬ごもり前の姿 |
|---|

|
■画像 d :20251127 ピラカンサ 気温が下がって来る秋の終わりに真っ赤に色づき 華やかに輝き始めます |
|---|

|
■画像01 :20251121 モミジの種子 種子はプロペラのような形をしており風に乗って 遠くへ飛んでゆきます。画像では左右が離れておりますが実際はつながっております |
|---|

|
■画像02 :20251121 三眼清水の木々も樹の上方から紅葉し始めております |
|---|

|
■画像03 :20251121コガモ 鴨川にはコガモが戻り賑わいを見せ始めております |
|---|

|
■画像04 :20251117 菊 菊は愛好家多く毎年丹精込めたて菊を育て、品評会に出品して 賞を受けることをたのしみにしている方、鑑賞を楽しみにしている方など人気の高い花です。画像の花は 畑の片隅を飾っている野菊 |
|---|

|
■画像05 :20251117 エンジェルトランペット 楽器のトランペットをした形で明るい黄色をしているが毒性を持っているので要注意 |
|---|

|
■画像06 :20251102ツバキ 画像は殻が割れて種子が現れている状態。種子は1つの殻 に最大9個の種子が入っていますが、それぞれの形も異なり通常は5,6個が凹凸を組み合わせ上手く入っております。画像は1つの実に見えますが各種子が組み合わさった形です。種子の用途も幅広く利用されております |
|---|

|
■画像07 :20251101コブドウトリバ T字型の体形が特徴10ミリ位の昆虫今年は少ないとは言え11月に昆虫が現れるとはと驚いている? |
|---|

|
■画像08 :20251101 オオホシカメムシ |
|---|

|
■画像09 :20251101ホソヒラタアブ 花の蜜を求めて現われます |
|---|

|
■画像10 :20251101 ツヤアオカメムシ |
|---|

|
■画像11 :20251101キタテハ |
|---|
2025/10月******************************************************

|
■画像01 :20251023 ミツバチ 花の蜜を集めている |
|---|

|
■画像01 :20251023 キコシホソハバチ だっこちゃんに似た顔をしています。だっこちゃんが分かる人は高齢者かな・・・・ |
|---|

|
■画像01 :20251010 キセキレイ |
|---|

|
■画像01 :20251012 ツマグロヒョウモン(オス) メスはヒョウモン柄の先が黒と白線の文様あり |
|---|

|
■画像01 :20251012クロウリハムシ つやつやした光沢が目に焼き付きます |
|---|

|
■画像01 :20251012オオシロカラカサタケ 危険:茎丈20センチ大きな毒キノコ 食べてはいけません |
|---|

|
■画像01 :20251012トホシテントウ 10個の星が6角形をしている |
|---|

|
■画像01 :20251012キボシカミキリ 右の触角を失っている この時期キズついた昆虫をたびたび見かけます |
|---|

|
■画像01 :20251012ホシホウジャク ホバーリングしながら蜜を吸っています |
|---|

|
■画像01 :20251012クマバチ 危険性を感じさせないハチです でも注意は怠らずに |
|---|

|
■画像01 :20251012モンシロチョウ |
|---|
2025/9月******************************************************

|
■画像01 :20250924k イトトンボ アジアイトトンボに似るが3センチ位の小さなトンボ画像不鮮明で詳細分からず |
|---|

|
■画像02 :20250918 ヒヨドリジョウゴ 花は可憐、秋には赤い実をつけ美味しく見えますが、毒を持っています。食べると危険です |
|---|

|
■画像03 :20250918 ホソオビアシブトクチバ |
|---|

|
■画像04 :20250918 ダンダラテントウ |
|---|

|
■画像05 :20250918 ミヤマアカネ 羽の先端の一部が薄く色が濃くなっている |
|---|

|
■画像06 :20250918 シラホシハナムグリ 樹液に夢中 |
|---|

|
■画像07 :20250918 チビタマムシ |
|---|

|
■画像08 :20250918 カブトムシ(メス)樹液に夢中 |
|---|

|
■画像09 :20250918 ホシホウジャク |
|---|

|
■画像10 :20250914 ノウゼンカズラ ブロック塀からつるをたらし陽をうけ咲き誇る花 |
|---|

|
■画像11 :20250906 ルリタテハ 美しい蝶なのですがボケ画像ごめん |
|---|

|
■画像12 :20250906 ヒメマダラミズメイガ |
|---|
2025/8月******************************************************
※8月猛暑:昆虫探しどころではない 休止日多し 皆さん気をつけましょう

|
■画像01 :20250801 モンクロシャチホコガ |
|---|

|
■画像02 :20250807 ハイマダラノメイガ |
|---|

|
■画像03 :20250812 ナミモンクモバチ 捕獲した獲物を後ろへ引きずり安全な場所まで移動 する、途中障害物に阻まれ獲物を失うことがある 行動を観察していると苦労している。 |
|---|

|
■画像04 :20250812 ダイサギ |
|---|

|
■画像05 :20250812 イトトンボ 拡大すぎてボケております |
|---|

|
■画像06 :20250812 キマダラカメムシ |
|---|

|
■画像07 :20250825 ヨツボシノメイガ 葉の裏側に止まるので普通のカメラでは撮影に苦労します |
|---|

|
■画像08 :20250825 ムラサキツバメ |
|---|

|
■画像09 :20250825 カゲロウ 森の中で光不足して画像がはっきりしてません |
|---|

|
■画像10 :20250825 コムラサキ 羽を広げれば薄い紫色をしている 頭が写っていないのが残念 |
|---|

|
■画像11 :20250825 アオスジアゲハ |
|---|
2025/7月******************************************************

|
■画像01 :20250705 スグリゾウムシ |
|---|

|
■画像02 :20250705 リンゴカミキリ |
|---|

|
■画像03 :20250705 テントウムシダマシ:食後の模様 葉の表面だけを食べている |
|---|

|
■画像04 :20250705 クサカゲロウの幼虫 |
|---|

|
■画像05 :20250705 マメコガネ |
|---|

|
■画像06 :20250705 ショウジョウトンボ・・・・真っ赤な体色が伝説上の怪物猩猩(ショウジョウ)を表している |
|---|

|
■画像07 :20250713 アオスジアゲハ |
|---|

|
■画像08 :20250713 ムラサキシジミ:青色が鮮やか 羽を広げた姿は珍しい |
|---|

|
■画像09 :20250713 オスグロトモエ |
|---|

|
■画像10 :20250713 ウリハムシ |
|---|

|
■画像11 :20250713 ニイニイゼミ:うるさく甲高く鳴きます |
|---|

|
■画像12 :20250727 コウゾハマキモドキ 前、後の区別が分りません |
|---|

|
■画像13 :20250727 カラスアゲハ |
|---|

|
■画像14 :20250727 ベッコウハゴロモ |
|---|

|
■画像15 :20250727 ミカドトックリバチ |
|---|

|
■画像16 :20250727 シロテンハナムグリ |
|---|

|
■画像17 :20250727 クロハナムグリ |
|---|
2025/6月******************************************************

|
■画像01 :20250601 アカガネサルハムシ |
|---|

|
■画像02 :20250601 クロトラカミキリ |
|---|

|
■画像03 :20250601 クロヒラタヨコバイ |
|---|

|
■画像04 :20250601 タマムシ |
|---|

|
■画像05 :20250601 シオヤアブ |
|---|

|
■画像06 :20250601 シギアブ |
|---|

|
■画像07 :20250601 ヨコズナサシガメ |
|---|

|
■画像08 :20250601 ヤドリバエ |
|---|

|
■画像09 :20250601 テングチョウ 鼻先がとがっている |
|---|

|
■画像10 :20250601 テングチョウ |
|---|

|
■画像11 :20250605 アカボシゴマダラチョウ |
|---|

|
■画像12 :20250605 クビアカトラカミキリ |
|---|

|
■画像13 :20250605 キベリクチボソハムシ |
|---|

|
■画像14 :20250605 アオスジアゲハ幼虫 |
|---|

|
■画像15 :20250605 ヒラタヤドリバエ |
|---|

|
■画像16 :20250612 ヨツボシヒョウタンナガカメムシ |
|---|

|
■画像17 :20250612 メダカナガカメムシ |
|---|

|
■画像18 :20250612 アカサシガメ |
|---|

|
■画像19 :20250612 トホシオサゾウムシ |
|---|

|
■画像20 :20250612 トビイロオオヒラタカメムシ |
|---|

|
■画像21 :20250612 チャオビヨトウ |
|---|

|
■画像22 :20250612 アミガサハゴロモ |
|---|

|
■画像23 :20250612 ビロウドコガネ |
|---|

|
■画像24 :20250614 チョウトンボ |
|---|

|
■画像25 :20250614 サトキマダラヒカゲ |
|---|

|
■画像26 :20250615 モンキクロカスミカメ |
|---|

|
■画像27 :20250615 クロスカシトガリノメイガ |
|---|

|
■画像28 :20250615 ヒゲコメツキ(♀) 触覚が棒状 オスの触覚は櫛状になっていて迫力があります。 |
|---|

|
■画像29 :20250615 イネカメムシ |
|---|

|
■画像30 :20250615 ムラサキシジミ |
|---|

|
■画像31 :20250615 ホソヘリカメムシ幼虫 |
|---|

|
■画像32 :20250615 ソトウスグロアツバ |
|---|

|
■画像33 :20250615 ヨコジマオオハリバエ |
|---|

|
■画像34 :20250626 スグリゾウムシ |
|---|

|
■画像35 :20250626 ?? 推測:クワガタの中間 |
|---|

|
■画像36 :20250626 クロバネツリアブ |
|---|

|
■画像37 :20250628 ナガゴフマカミキリ |
|---|

|
■画像38 :20250628 チョウトンボ 5,6匹のトンボが飛び回り動きに追いつけません 焦点が合っておりません |
|---|

|
■画像39 :20250628 シオヤアブ♀ |
|---|

|
■画像40 :20250628 ハムダマシ |
|---|
2025/5月******************************************************

|
■画像 29:20250521 ハナアブ |
|---|

|
■画像 28:20250521 キマダラカメムシ |
|---|

|
■画像 27:20250521 カミキリムシ 「ジョウカイボ:足の付け根黒い 翅が柔らかい」 |
|---|

|
■画像 26:20250521 ヤマボウシ 秋葉の森 |
|---|

|
■画像 25:20250518 畑一面に咲いたポピー |
|---|

|
■画像 24:20250518 カタツムリ:素手で触ってはいけません |
|---|

|
■画像 23:20250518 モモノゴマダラノメイガ |
|---|

|
■画像 22:20250518 モンクチビルテントウ |
|---|

|
■画像 21:20250518 ナミテントウ |
|---|

|
■画像 20:20250518 コカメノコテントウ |
|---|

|
■画像 19:20250518 クチブトカメムシ 幼虫 |
|---|

|
■画像 18:20250518 ヨツボシテントウダマシ |
|---|

|
■画像 17:20250515 タケノホソクロバ |
|---|

|
■画像 16:20250515 キジ |
|---|

|
■画像 15:20250515 オオミズアオ |
|---|

|
■画像 14:20250515 ヒメマルカツオブシムシ (初掲載) |
|---|

|
■画像 13:20250515 ヤナギルリハムシ (初掲載) |
|---|

|
■画像 12:20250515 アシナガバエ |
|---|

|
■画像 11:20250515 ギンツバメ 蛾です蛾の紋様は蝶に比べ緻密で関心します |
|---|

|
■画像 10:20250515 キイロトラカミキリムシ (初掲載) |
|---|

|
■画像 9:20250515 ヒメアカタテハ |
|---|

|
■画像 8:20250515 ヨツボシアリモドキ |
|---|

|
■画像 7:20250515 トラフムシヒキ |
|---|

|
■画像 6:20250515 ルリチュウレンジ |
|---|

|
■画像 5:20250515 ツルバラ垣根 美しいバラにはトゲがあると言われ 泥棒も近づくことをた美しくても侵入をめらうでしょう |
|---|

|
■画像 4:20250504 削除 |
|---|

|
■画像 3:20250504 ムーアシロホシテントウ |
|---|

|
■画像 2:20250504 ヒメカメノコテントウ 紋は色々 |
|---|

|
■画像 1:20250504 カオジロヒゲナガゾウム |
|---|
2025/4月******************************************************

|
■画像 31:20250427 クレマチス つる性、大輪の花 |
|---|

|
■画像 30:20250427 ゾウムシ |
|---|

|
■画像 29:20250427 ナミガタチビタマムシ |
|---|

|
■画像 28:20250427 ヒゲナガ |
|---|

|
■画像 27:20250427 サビキコリ |
|---|

|
■画像 26:20250427 ナミアゲハ |
|---|

|
■画像 25:20250426 コチドリ スズメの大きさで素早く歩く 渡り鳥のように一カ所にとどまることなく移動する旅鳥 個人的には鴨川で初観察 |
|---|

|
■画像 24:20250426 ホソヒラタアブ |
|---|

|
■画像 23:20250426 ヒゲナガハナバチ |
|---|

|
■画像 22:20250424 チビタマムシ |
|---|

|
■画像 21:20250424 クロヒラタヨコバイ なかなか味のある姿に頬が緩む |
|---|

|
■画像 20:20250424 アカサシガメ |
|---|

|
■画像 19:20250417 ヤマトカギバ |
|---|

|
■画像 18:20250419 キンランソウ |
|---|

|
■画像 17:20250419 オオウンモンクチバ |
|---|

|
■画像 16:20250419d シロスミレ |
|---|

|
■画像 15:20250419 ナミガタチビタマムシ |
|---|

|
■画像 14:20250417c ??ワカラナイ |
|---|

|
■画像 13:20250417 アオサギ |
|---|

|
■画像 12:20250419g ハナバタケ 色とりどり春の花が満開 毎年近くの幼稚園児が訪れます |
|---|

|
■画像 11:20250416 ミツボシツチカメムシ |
|---|

|
■画像 10:20250416 ムシヒキアブ |
|---|

|
■画像 09:20250416 コカメノコテントウ |
|---|

|
■画像 08:20250416 アカヒメヘリカメムシ |
|---|

|
■画像 07:20250416 キアゲハ |
|---|

|
■画像 06:20250416 オビコシボソガガンボ |
|---|

|
■画像 05:20250416 ??? |
|---|

|
■画像 04:20250412 ??ゾウムシ 昆虫の種別名が判明しません |
|---|

|
■画像 03:20250405 落葉の葉が地面に落ちないで、サメの形に成形された自然作品です。 時には違う角度から何かを探すように見て歩くのも自然を楽しむ一つです |
|---|

|
■画像 02:20250405 ベニバナトキワマンサク 樹木全体が紅色に染まり、淡い桜の花があれば 良かったのですが少し離れていました。 |
|---|

|
■画像 01:20250405 メジロが桜の樹の中で忙しく飛び回って落ち着きません、カメラに収めるのに苦労しました。 |
|---|
2025/3月******************************************************

|
■画像 01:20250327 カワセミ 例年になくカワセミに出会う機会が多くなっております。しかしカワセミを引き立てるバックの風景が雑木や枯れ草ではすっきり感がなく残念です。
|
|---|

|
■画像 02:20250323 アネモネ 細長い花壇に個々人が好みの花を咲かせ春には花が咲き 道行く人は立ち止まり楽しんでおられます
|
|---|

|
■画像 03:20250323ヒメリュウキンカ 花ビラに光沢のある珍しい花 |
|---|

|
■画像 04:20250322 ハッカハムシ 土の中から這い上がってきたばかりです 無地柄の規則正しい斑点が翅全体を飾っています
|
|---|

|
■画像 05:20250322 オナガ 尾の長い ギーギーと鳴きうるささを感じる
|
|---|

|
■画像 06:202500320 ジンチョウゲ 香り高く春の花
|
|---|

|
■画像 07:20250320 ホウジロ 樹木の頂点に留まり縄張りをアピールしているのか鳴き続けます
|
|---|

|
■画像 08:20250319 雪景色:午前中に雪が降り始め落葉樹木も雪化粧
|
|---|

|
■画像 09:20250319 カラスの足跡
|
|---|

|
■画像 10:20250319 雪だるま 子供たちも久しぶりの雪遊び
|
|---|

|
■画像 11:20250318スイセン 最近は花の形も大型化していて見応えがあります
|
|---|

|
■画像 12:20250318 濃紺で光沢あり 美しいが名は???
|
|---|

|
■画像 13:20250312-スズメ 野鳥の姿が減り続けているなかにおいてスズメは環境にされない柔軟性があり減少は感じません
|
|---|

|
■画像 14:20250301 モズ
|
|---|

|
■画像 15:20250301変顔 樹木のこぶです悲しそうな表情 右足を前に出そうとしています 頑張っている姿に声援を送りたい 此は自然が作り出した芸術作品
|
|---|
2025/2月******************************************************

|
■画像 A:20250223 タシギ先月も掲載しましたタシギ今月は2羽で川の浅瀬で餌探しクチバシが長いので
泥の中に差し込み餌を探します
|
|---|

|
■画像 B:20250220 キセキレイ 胸から腹にかけて黄色をしている 水辺で見かける野鳥ですが珍しく鬼カワラの
上で一休み
|
|---|

|
■画像01:20250220 ゴイサギ 後頭部から飾り翅が1本伸びております
|
|---|

|
■画像02:20250220 ジョウビタキ
|
|---|
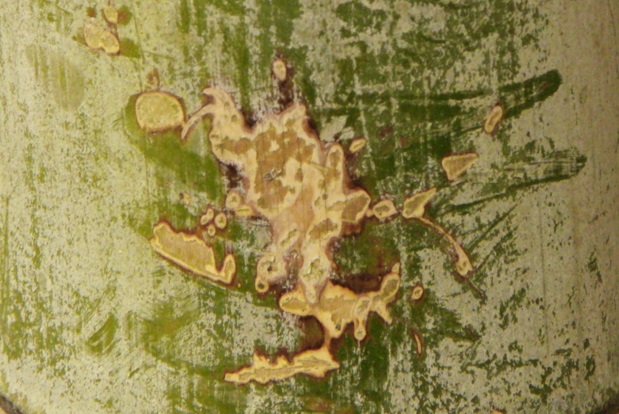
|
■画像03:20250216その他1 竹に描かれた紋様 動物に見えますが判定出来ません。これも自然(風雨、気温、湿度)が作り出す自然美
|
|---|

|
■画像04:20250216セ ハクセキレイ 翅の裏側が水面に映され珍しい写真になりました
|
|---|

|
■画像05:20250215イソシギ 逆光で暗い:修正は致しません
|
|---|

|
■画像06:20250214カワセミ 逆光で暗い:修正は致しません
|
|---|

|
■画像07:20250203-t04 カワセミ
|
|---|

|
■画像08:20250203-t03 マガモ 久しぶりに鴨川につがいで姿を現しました
|
|---|

|
■画像09:20250201ジョウビタキ
|
|---|

|
■画像10:20250201-art02 竹の表面に現れた抽象的な絵に魅了されました
|
|---|

|
■画像11:20250201-art01 竹の表面に現れた抽象的な絵に魅了されました
|
|---|

|
■画像12:20250201-t06 カワセミ 三貫清水の北池に姿を見せました
|
|---|

|
■画像13:20250201-t05 ジョウビタキ
|
|---|

|
■画像14:20250201-t02 カワセミ
|
|---|
2025/1月******************************************************

|
■画像01:20250125-t001 タシギ:タシギとしましたが、体型は小さく色が薄いために疑問が残っています。
|
|---|

|
■画像02:20250125-t002 マガモ:つがいで久しぶりに鴨川へやってきました。
|
|---|

|
■画像03:20250102 イソシギ
|
|---|

|
■画像2:20250102 カイツブリ 水に潜り餌を何度も繰り返す
|
|---|

|
■画像3:20250102 カワセミ 正月の工事休みでカワセミが戻ってきた
|
|---|

|
■画像4:20250102 バン
|
|---|

|
■画像5:20250107 アオサギ 何時間も同じ姿勢で立っている
|
|---|

|
■画像6:20250107カワウ カワウは真っ黒な姿なのに頭と翅の一部分が白くて交配による変異なのか
珍しい姿に驚く
|
|---|

|
■画像7:20250107 カワセミ
|
|---|

|
■画像8:20250107 カワセミ
|
|---|

|
■画像9:20250107 コサギ/鴨/カワウ 3種の野鳥が等間隔に並んだ珍しい姿に驚き!
|
|---|

|
■画像10:20250107 マガモ 頭がモスグリーンで光沢があってひときわ目立ちます
|
|---|

|
■画像11:20250110 カワウ:頭、首から胸にかけて白くなっている珍しい
|
|---|

|
■画像12:20250114 オナガ名前の通り尾が長い、姿に似合わず鳴き声は美しくはありません
|
|---|

|
■画像12:20250114 オナガ 太陽の光を受けるとスマートさが際立つ 逆に尾の先が白いのが見えない
|
|---|

|
■画像13:20250114 セグロセキレイ 尾をリズム似合わせたように上下に動かす
|
|---|